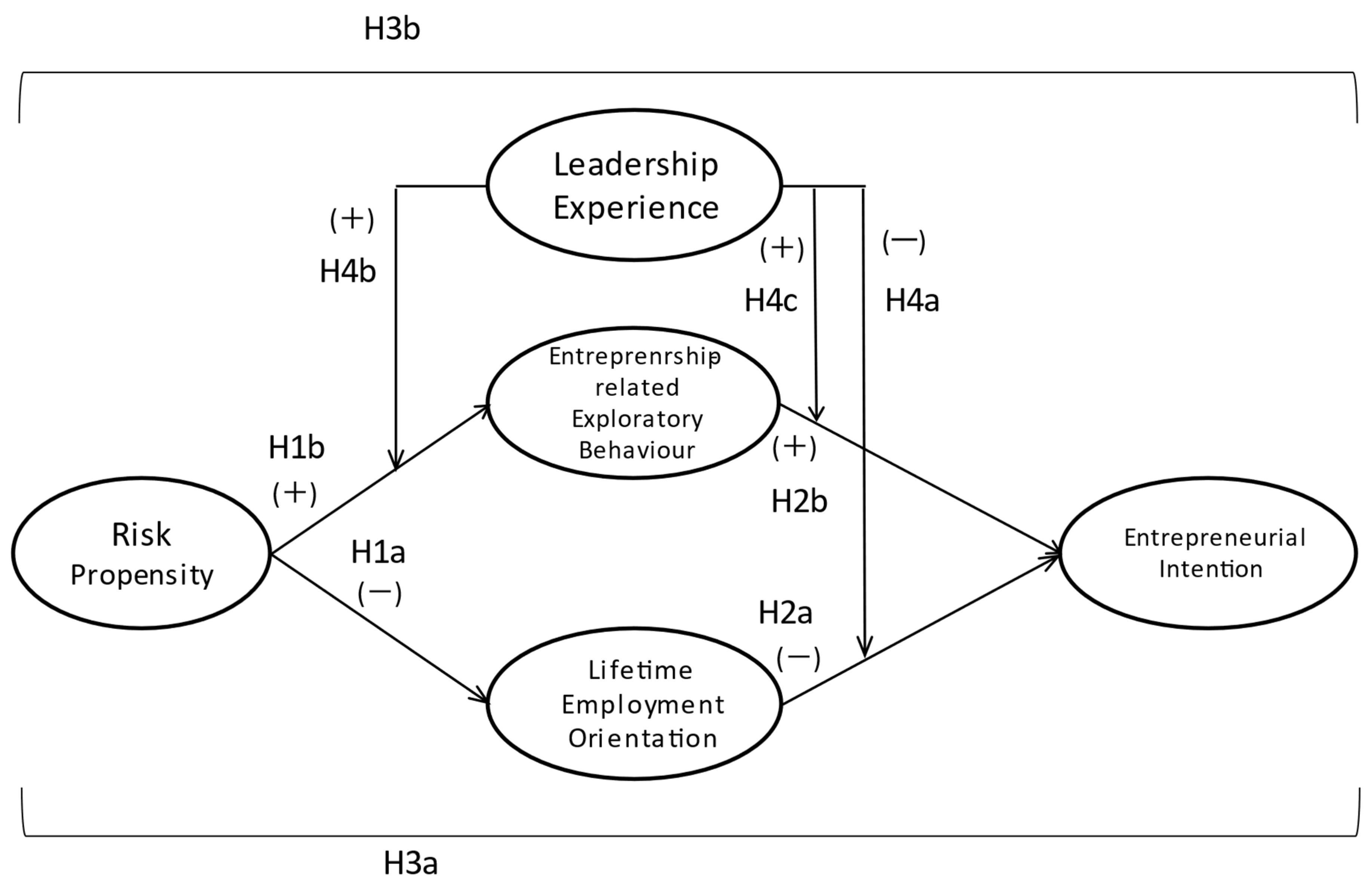今回は、因果複雑性の経営学の根幹をなす構成論アプローチのエッセンスを解説する。前回書いたように、還元主義、線形性、対称性、純効果主義といった方程式的というか線形代数的な発想に支配された形で構築された従来の経営理論ではなく、経営現象における因果関係は、本質的にそのような単純な要素間の関係には還元できるものではないと考える新しい経営学のアプローチを、因果複雑性の経営学と名付けることにする。因果複雑性の経営学では、経営現象は様々な要素が組み合わさることによって生じることを前提とする。いろんな要素が組み合わさることによって、個々の要素に還元してそれを足し合わせるだけでは説明ができない因果関係が生じるので、因果複雑性というのである。自然科学のたとえを用いるならば、天体を点にまで還元してしまって考えるような発想ではなく、化学結合によって個々の分子とはまったく異なる特徴や作用をもった物質ができあがるような発想を経営学にも用いるわけである。
構成論アプローチを一言で言えば、さまざまな要因が複雑に組み合わさることで結果が起こると考えるアプローチで、経営学でもかなり前から提唱はされていたが、それほど発達はしてこなかった。その理由は、前回でも書いた通り、経営学の理論が実証研究で用いるツール、例えば、数学や統計モデルと不可分である中で、構成論アプローチを支える数学や統計モデルが未発達だったからである。数学は、究極的には論理の学問であるので、数学の論理が、経営理論の論理に影響を与えることは必須なのである。つまり、いくら概念的に構成論アプローチを提唱したとしても、具体的に構成論に基づいた経営理論を構築したり、それを現実の世界で実証しようとするときに、方程式的な思考、線形代数的な手法を当てはめようと試みてもうまくいかないのである。しかし、近年、この数学的な視点、分析手法において革新的な動きが見られたために、構成論アプローチが一気に発展した。Misangyi, Greckhamer, Furnari et al. (2017)は、これを、数学的手法が未発達であった時代のものと区別する上で「新構成論アプローチ」と呼んでいる。
ではまず、構成論アプローチで前提とする「因果複雑性」について説明しよう。因果複雑性の考え方は、前回述べたような「還元主義」「線形性」「対称性」「純効果主義」とは全く異なる因果関係の考え方を採用する。それらを表すキーワードを並べると、因果関係の「結合性」「等値性」「非対称性」となる。結合性とは、方程式や線形代数のように還元された各独立変数が従属変数の原因となっており、それを足し合わせることで結果が出ると考えるのではなく、特定の要素が特定のパターンで組み合わさって初めて結果の原因となることがあるという意味である。すなわち、回帰分析のようなアプローチで調べても効果は検出されないのに、何か別の要素と結びつくと、あたかも化学反応が起こって別の性質が生まれたかのように、結果に影響を与えるのである。これは、2つの要素とは限らない。3つ、4つ、5つの要素が組み合わさって原因となるということも当然想定する。実証研究的にいうならば、線形代数に依拠する重回帰分析では、2次元交互作用や3次元交互作用という手法があるが、4次元、5次元となってくるとお手上げである。
次に「等値性」であるが、これは、ある結果をもたらす要素の組み合わせが唯一存在するわけではなく、いくつかの別の組み合わせによっても同じ結果が出ることがあると想定することを意味する。これは、実際の企業経営において、特定の状況下において企業業績を高めるベストな方法は1つしかないと考えるのに無理があることを考えればある意味自明な前提である。企業業績を高める経営戦略はいろんなものが存在するし、そのどれをとっても業績が上がる可能性はある。また、アントレプレナーシップ分野においてエフェクチュエーションというコンセプトが流行りつつあるが、アントレプレナーが利用可能なリソースはそれぞれ異なっているから、「成功するためにはこれとこれの組み合わせがベストです」という発想は非現実的である。成功するためのリソースの組み合わせのパターンはいろんなものが存在すると考える方が現実にあったロジックである。このようなロジックを方程式的に、あるいは線形代数的に表現するのは極めて困難である。
そして、因果関係の「非対称性」を理解するためには、古い経営学に馴染んだ私たちの頭を支配している「線形性」「相関関係的な思考」をアンラーニングする必要がある。前回も述べた、従来の経営学が前提とする「対称性」は、Xが増加するとYも増加する、Xが減少するとYも減少するといったように、Xが増加する効果と、Xが減少する効果は方向が違うだけで基本的に対称であると考える。正比例のようにXとYの関係が直線的なので対称性があるのである。この因果関係は当たり前にように見えるが、それは私たちの頭がその発想に毒されているからであって現実は必ずしもそうではない。例えば、Xが多くても(あるいは存在しても)、少なくても(あるいは無くても)、他の条件が揃うと結果が出ることがある。あるリソースが豊富な企業も、欠如している企業も、それぞれにおいて適切な戦略と組み合わせれば業績が向上するというケースだと、そのリソースの増減と業績の上下は相関関係にないことは明らかである。結合性、等値性と組み合わせていうと、特定の結果を生み出す組み合わせが複数あり、その結果を生み出さない組み合わせも複数ある場合、その組み合わせは必ずしも単純な対称関係にあるわけではない。
相関関係的なイメージに囚われていると混乱してきたかもしれないが説明を続けよう。上記の非対称性は、ある条件が存在しない(低いと)と結果は生まれない(小さい)が、その条件が存在しているからといって(高いからといって)結果が生まれる(大きい)とは自動的には言えないことも示している。これは、その要素あるいは複数の要素の組み合わせが特定の結果を生み出す「必要条件」であることを意味している。これは、XとYが線形性を基本とする相関の関係になっている状態とは異なっている。その要素が存在しない(小さい)ときには結果が生じないことは言えるが、その逆は言えないので非対称的である。同様に、特定の要素あるいは複数の要素の組み合わせが生じていれば必ず結果が生まれるという「十分条件」の場合、等価性でも説明した通り、その組み合わせでなくても結果が生じることがありうるので、それは必要条件ではない。つまり、それらの組み合わせによって結果が生じることは言えるが、その逆は言えないので非対称的である。
経営理論を構築しようとする人間の思考が方程式的、線形代数的、相関的なものに支配されていると、上記のような必要条件と十分条件が組み合わさったような理論構築はできない。しかし、現実の経営実践では、このような現象は山ほどあるので、これらを経営理論に反映できないのであれば、経営理論は無力としか言いようがない。例えば、ボトルネックという概念がそうである。これは、ある変数と結果に相関関係がないからといって、その変数は結果と無関係であるということではなく、その変数が欠如していると、他にどんな条件が整っても結果が生じないという現象である。企業がいくら優れた戦略やビジネスモデルを考案できても、それを実行できる人材がいないと企業業績は上がらない。逆に、それを実行できる人材がいるからといって、企業業績が自動的に上がるわけではなく、優れた戦略やビジネスモデルが伴わないと結果が出ない。これは、特定の人材がボトルネック(必要条件)になっているケースで、実務家であれば当たり前のロジックであるが、従来の経営理論ではこのようなロジックや思考を駆使した理論構築ができなかったのである。
十分条件についても、その要素があると必ず結果が生じるが、それがないからといって結果が生じないとは言えないので、その要素と結果は比例しておらず相関関係ではない。よって、相関分析をしても有意な結果にはならない。ある戦略と特定のタイプの人材の組み合わせが企業業績を高める十分条件であることが分かったとしても、別の企業にはそれがないから希望がないというわけではない。等価性の原則のとおり、別の戦略と別のタイプの人材の組み合わせでも企業業績が高まる可能性が十分にある。つまり、従来の経営理論の前提を支配していた相関関係というコンセプトは、ある要素と結果の因果関係が、必要十分条件であるときのみという特殊ケースしかカバーできていなかったことになるのである。つまり、因果複雑性を捉えた理論になっていなかったのである。次回は、今回説明した構成論アプローチと因果複雑性の経営学の発展に寄与した数学的思考法について説明する。
文献
Fiss, P. C. (2007). A set-theoretic approach to organizational configurations. Academy of Management Review, 32(4), 1180-1198.
Furnari, S., Crilly, D., Misangyi, V. F., Greckhamer, T., Fiss, P. C., & Aguilera, R. V. (2021). Capturing causal complexity: Heuristics for configurational theorizing. Academy of Management Review, 46(4), 778-799.
Misangyi, V. F., Greckhamer, T., Furnari, S., Fiss, P. C., Crilly, D., & Aguilera, R. (2017). Embracing causal complexity: The emergence of a neo-configurational perspective. Journal of Management, 43(1), 255-282.